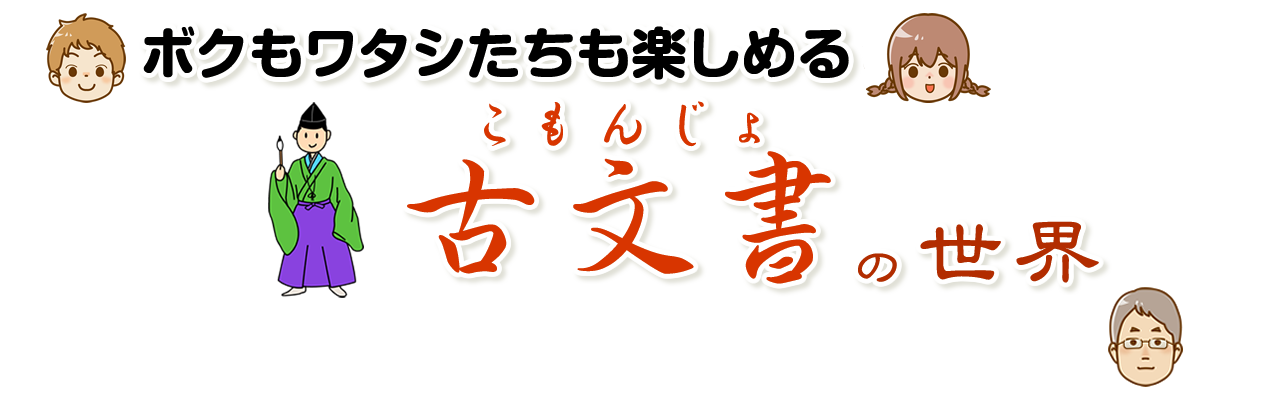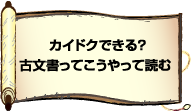-古文書探検隊(たんけんたい)が行く-
古文書って古い文書(手紙のこと)って書くけど、どんなものなんだろうね。

鎌倉時代(じだい)のものっていうことは、そうとうに古いものだね。
でもね、古ければなんでも「古文書」っていうわけではないんだ。
最初(さいしょ)に、どういうものが古文書なのかを知っておこう。

えっ?古い文字が書いてあれば古文書じゃないの?

もしかしたら、古文書と言える物には決まりがあるの?
最初(さいしょ)にそれを覚(おぼ)えておこう。
古文書とは、「だれかが、だれかにあてて書いたもの」のこと。
まず思いうかぶのは手紙だよね。
その他にも、約束(やくそく)事を書いた物や、命令(めいれい)書もそうなんだ。
用件(ようけん)と、書いた人(差出(さしだし)人)と受け取る人(宛先(あてさき))の名前、日づけが書かれた物を文書(もんじょ)っていうんだ。
その中で、比較的(ひかくてき)古い、史料(しりょう=過去(かこ)のことを調べるための材料(ざいりょう))となるもののことを古文書と言うんだよ。

差出人や日づけが書いていないものは古文書とは言えない。
つまり、俳句(はいく)や和歌を書いた短冊(たんざく)や掛(か)け軸(じく)、小説(しょうせつ)、地図などは、宛先は書いてないよね。
日記にも日づけは入っているけれど、差出人や宛先が書いていないから、古文書とは言わないんだ。
こういった物は、古記録(こきろく)っていうんだよ。

古文書だけではなく、たくさんの美術(びじゅつ)工芸品(こうげいひん)や、楽器(がっき)など、日本国内外の貴重(きちょう)な物が保存(ほぞん)されているよ。
つまり日本のお宝(たから)の宝庫(ほうこ)だ!
古文書は、歴史(れきし)学の中で “古文書学” として研究されているんだ。
その中で対象(たいしょう)となっているものは、近世=17世紀(せいき)頃(ころ)から、開国の1854年まで=のものが圧倒的(あっとうてき)に多いんだ。
けれども、中世=12世紀初頭(しょとう)から16世紀末(まつ)頃=の物も見つかっているし、それより昔の8世紀に立てられた正倉院(しょうそういん)にも文書が残(のこ)っていたんだよ。
中国をはじめとして、世界各地(かくち)では、もっと古い物も見つかっているんだ。

このページで学んだことのポイントはこれだ!
整理しておくよ。
〇だれかがだれかにあてて書いた物
〇差出人、宛先、日づけ、用件が書いてある物
〇比較的古い、史料となるもの

やっぱり古い文字が書いてあるのが古文書だったんだね。
でも古い文字だけじゃダメだったんだ。

うん。古文書と呼(よ)ばれるための条件(じょうけん)があったんだよね。
でも、紙に書かれた物なら、ボロボロになりやすいような・・・

そう。古文書という物には条件がある。
それでは、ボロボロにならないようにはどうすればよいのかな?
ボロボロになってしまったらどうしよう?
この先のページで、それを調べてみようね。